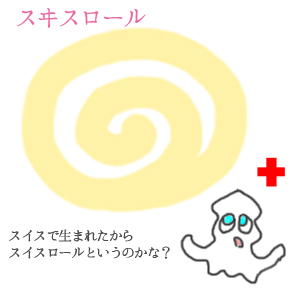名古屋の中古CD店でみつけたアーノンクールのベートーヴェン第九。なんと投売りの324円(税込)で、こういうのを掘出しモンというんでしょうか……
で、さっそく聴いてみました。アーノンクールさんは、ついこの間(2016年3月5日)お亡くなりになったばっかりで、ホントなら、CD売場に特設コーナーができてもいい感じなんですが、ここでは300円投売り……カワイソウ……というか、得したなあというか。

アーノンクールというと、古楽ファンにはよく知られた名前……というか大御所なんですが、最近ではベルリンフィルとかウィーンフィルとか、いわゆるモダンオーケストラも指揮して、モーツァルトからベートーヴェン、さらにはロマン派まで……ついに「巨匠」と呼ばれる方々の仲間入り……
しかし、経歴を見ると、この方、1952年から1969年までウィーン交響楽団(ウィーンフィルではない)のチェロ奏者だったということで、一旦古楽に入ってぐるっと大回りの道をたどって、だんだん現代に近づいていって、ついに「巨匠」として復帰……そんな見方もできるのかな?
ということで、聴いてみました。なるほど……えらくスッキリした演奏で、かつての第九の、重戦車隊が地を轟かせて迫ってくるイメージとはかなり違う。まあ、演奏がヨーロッパ室内管弦楽団ということで、オーケストラメンバーの数からして違うから……ということもあるのでしょうが、タメがなく、コダワリがなく……しかし、決めるところはガツンと決めてる印象。
合唱も、現代音楽を得意とするアーノルト・シェーンベルク合唱団ということで、スッキリしてます。第九の第四楽章で、ソプラノのおどろおどろしいビブラートでげんなりした経験のある私でも、この合唱団なら許せる……許せるって、大きく出たもんですが、あの過剰テルミンみたいなビブラートは、クラシックに免疫のない人が聴いたらだれでも気持ち悪くなるんじゃなかろうか……
まあ、そういう過剰ビブラートもなくて、歌の面でもスッキリ……して、いい演奏……のはずなんですが、なぜかあんまり感動しなかった。なんでだろう……まあ、ベートヴェンの第九、ほんのわずかしか聴いてないから比較もできないんですが……でも、今まで聴いた中では、やっぱりフルトヴェングラーの1951年バイロイト録音と、1989年バーンスタインのベルリンの壁崩壊コンサートのCDがダントツにすごかった……

そういう「巨峰的録音」にくらべると、このアーノンクール盤、なんか魅力が乏しい……まあ、これは、私の耳がクラシックの世界に慣れてないというか、圧倒的に聴いてる数が足りないからかもしれませんが……でも、自分で感じたところは偽れません。やっぱりフルトヴェングラー盤の岩山大崩壊のあのド迫力や、バーンスタイン盤の、奏者全員がなんかに取り憑かれたかのような超常現象的録音とくらべると……
で、思ったんですが……このベートヴェンの第九って、演奏の善し悪しとかの音楽的範疇をやっぱり少し超え出たところで、その魅力が決まるんじゃないかな……と。フルトヴェングラー盤は世界中を巻きこんだ第二次大戦がようやく終結して数年、ナチに協力したという嫌疑をかけられてたフルトヴェングラーが、いろんな複雑な思いを一杯に呑み込んで、音楽でドカーンと噴火させた解答……そしてバーンスタイン盤はヨーロッパ諸国とアメリカ、つまり西洋世界の戦後が終わってベルリンの壁崩壊とともに輝く未来が……
今となってみれば、そういう「未来」は訪れなかったことはほぼ決定的ですが、あの当時は、西洋世界の人じゃなくても、たとえば日本人なんかでも、なんか雪どけというか、ああ、ようやく桎梏に満ちた世界が終わって、新しいすばらしい世界が開けてくるんじゃないか……そんな、今から見れば根拠のない期待感というか展望といいますか……
それが証拠に、バーンスタイン盤では、元の歌詞の「 Freude」(フロイデ・喜び)の部分を「Freiheit」(フライハイト・自由)に変えて歌っています。クラシックの世界では、オリジナルテキストは絶対だから、これはよくよくよほどのこと……つまりそれだけ、「あの瞬間」は特別だったんですね。バーンスタイン自身が、ライナーノーツでそんなことを書いてるし。

ということでこの第九、やっぱり音楽以外の要素と申しますか、なにか大きな流れに関係してある存在みたいな……そこまでいうと大げさかもしれませんが、「じゃあ次の演奏会は第九やってみようか」という感じでは決められないような……ただ、なぜそうなるのかということを、第九の音楽的な構造からさぐっていければ……
音楽的構造による解析!……むろん、こういうことは、私みたいなシロウトじゃなくて、音楽をやってる人とか、音楽を研究している人がやるべきだし、もうすでにかなり解明されているのかもしれません。私が知らないだけで……ただ、私もシロウトながら、あっ、こういうことかもしれない……と気づいたこともあるので、今回はそれを書いてみようかな……と。
そういうことで、まず第一楽章の冒頭から。ここに鳴る弦の5度下降。この曲を最初に聴いたとき、なんてとりとめもなくはじまるんだろう……と思ったことを覚えてます。なんか、まともな曲のはじまりじゃなくて、オーケストラがまちがえたみたいな、あるいは音合わせをやり続けてるような……しかも、その感じがなんとなく不安で、頼りなげで、なんかカゲロウが死んでふわっと落ちてくるみたな……あとで知ったんですが、これがあの有名な「空虚5度」のオープニングでした。

空虚5度……これについては、前に書いたことがあります。リンク 現代人の耳には、5度の和音が虚ろな響きに聴こえる(ロックでいう、パワーコード)……この第九交響曲は、調性がニ短調(D minor)ということで、ニ短調だと主音がDで5度(属音)は A になる。なので、主音から属音への下降形は D↓A になるはずなんですが、実際に鳴る音は E↓Aです。これはふしぎだ。なんでこんなことをしたんだろう……E↓A だと、3度に C をとればイ短調(A minor)あるいは C# をとるならイ長調(A major)、このどっちかになるはず……

主音の D から5度上がると A だけど、D から下の A への下降は 4度になる。空虚5度を鳴らすためには、Dから A に降りるのではダメで、一つ上の E から A に降りないといけない……そういうことで、E↓A と鳴らしているのだろうか……ところが、このカゲロウのような不安定な音型の後にフォルテで出てくる第一主題は主調のニ短調の D↓A の下降型になってます。

このあたりの問題は、正直よくわかりませんが、最初の下降音型で5度を表現したかったのではないか……これは、実は第四楽章に深く関連していて、第四楽章のあの有名な「歓喜の歌」の途中で、まさにこの5度の下降音型 E↓A が出てくるんですが、私が読んだり調べたりした範囲では、このことに触れたものは見当たりませんでした。もしかしたら新発見?
いや、まさか……これだけ細部まで研究され尽くしているベートーヴェンの第九に、もういまさら新発見はないだろうから、絶対にだれかがどっかで書いてるはずなんですが(つまり、私の調べ不足)、この第一楽章冒頭の5度の下降音型と第四楽章の歓喜の歌の途中で出てくる同じ5度の下降音型は、絶対に関連しているとしか思えません。というのは、歌詞までがそこを表現するようにつくってあるから……
第四楽章の「歓喜の歌」は良く知られたメロディーですが、その中に、一回だけ、この E↓A 下降音型が出てくる場所があります。そして、そこに対応する歌詞は……というと、「streng geteilt」。シュトレンゲタイルト、強く分けられた、という意味のところです。ここに対する音型は、streng(D)↑ ge(E)↓ teilt(A)となっており、主音 D から E に上がり(2nd)、E から A に 5度(5th)の下降を見せます。

geteilt(ゲタイルト)は、動詞 teilen(タイレン・分ける)の過去分詞で、「分けられた」という意味。この箇所の全体は「Was die Mode streng geteilt」で、Mode(今の風潮・規範。つまり石頭の考え)によって強く分かたれたもの、あるいは、Mode が強く分けへだてたもの、という意味になると思いますが、これが、天国(エリジウム)の乙女の魔法によって再び結ばれる(binden wieder)ということです。全体を書くと、次のようになります。

これは、良く知られているように、ベートーヴェンがシラーの詩を(一部改変しつつ)テキストとして使っているわけですが、この「歓喜の歌」は主音 D の3度上の F# から始まり、F#↑G↑A(Freude, Schöner)__A↓G↓F#↓E(Gotterfunken)__D↑E↑F#(Tochter aus)__F#↓E(Elysium)__F#↑G↑A(Wir betreten)__A↓G↓F#↓E(Feuertrunken)__D↑E↑F#(Himmlische dein)__E↓D(Heilligtum)というふうに、主音 D と属音 A の間を行ったりきたりで、この5度圏内からは出ません。
そして、この5度圏内で、常に中心にあるのが3度の F#音。ニ長調(D major)なので、主音はむろん D なんだけれど、このメロディーにおいては、ニュートラルの位置にあるのが実は3度の F# 音で、この F# 音は、剣豪が常にニュートラルの位置から刃をくりだすように、あるいはロボットアームがどんな動作をする場合にも常に一旦ニュートラルの位置に帰ってから次の動作をするように、全体の動作を常時コントロールするベースとなっている……そんな感じを受けます。
これは、実際にこのメロディーをピアノの鍵盤で鳴らしてみると、なるほど……と体感できます(中指を F# に置くと、右手の五本指で簡単に弾ける。中指が全体の支点になり、右の薬指と小指、左の人差指と親指が、天秤のようにきれいにバランスをとる)。これは、メロディーのはじまりのFreude、そしてなかほどのElysium、Wir、(Himmli)sche dein と、強拍になる部分に常に3度のF#音がきているから、ベートーヴェンがかなり意識して使っていると私は思うのですが、いかがでしょうか。

エリジウムの乙女の魔法が、Mode が強く分けへだててしまったものを、再び結びつける……こういう意味で、全体としては肯定的なんですが、「強く分けへだてた」という否定の部分で E↓A の5度下降音型を、ここぞ!とばかりに使っています。そして、この歓喜の歌では、ここだけが「D – A」の5度圏域を飛び抜けて下の A に落ちる。この箇所がなければ全体が「D – A」の5度圏域に納まったものが、ここがあるために全体がオクターブ8度圏域になってしまいます。
そしてまさに、この E↓A の下降音型は、この第九の冒頭の第一楽章で出てきた、あの空虚5度の E↓A にほかならない……こうして考えてみると、ベートーヴェンは、この第九交響曲を、空虚5度の E↓A で開始し、第一楽章、第二楽章、第三楽章……ときて、ついに第四楽章の歓喜の歌で F#(3度)の全面肯定に至った……この歓喜の歌の中で、唯一否定的な歌詞である「強く分かたれた」streng geteilt の部分には E↓A の下降音型をわざわざ用いて最初の空虚5度を思い起こさせるものの……
それもすぐに鳴る F#(3度)で再び全面肯定されます。F#↑G↑A(Alle Menschen)__A↓G↓F#↓E(werden Brüder)__D↑E↑F#(Wo dein sanfter)__E↓D(Flügel weilt)すべての人は兄弟となる。汝(エリジウムの乙女)のやわらかな翼の憩うところ(エリジウム)で。
このように考えてみると、この交響曲はまさに5度と3度の主導権争いであって、5度は第一楽章と第二楽章をずっと支配し続ける。これに対して第三楽章は、調性B♭になるものの3度(長3度)の無意識的な肯定(そうです!第三楽章は、ベタな3度の肯定になってる……)、そして第四楽章において、最終的に5度と3度をさらに高い位置から比較した結果としての、知性による3度の意識的な肯定……そんな図式になっているのかな……と、まずは思うのですが(後になるとちょっと考えが変わる)。
そして、ここでやっぱり思い出すのが、音律と和声の話。ヨーロッパ音楽の音律は、中世においてはピタゴラス音律に基づく教会旋法であって、単旋律聖歌が延々と歌いつがれてきたわけですが、12世紀において対位法ができてくるとともに、5度が意識されるようになった。ピタゴラス音律においては、うなり(ビート)なしにきれいに響くのは8度(オクターブ)と5度だけで、これだけが「和声」として認められていたということだった。(あと、補足的に4度も)
しかし、14、15世紀(いわゆるルネサンス)に入ると、これまでは不協和音と考えられてきた3度や6度が和音の仲間入りをしてきます。そして、3度や6度がきれいに響かないこれまでのピタゴラス音律に変わって、純正調や、3度や6度、とくに3度の響きが美しいミーントーン(中全音律)が支配的になってきます。
なぜ、こういう現象が起こってきたのか……そこのところをわかりやすく解説してくれている本がありました。作曲家の藤枝守さんの『響きの考古学』(平凡社ライブラリー)。以下、少し引用してみます(pp..85-86)。
(引用はじめ)………………………………
ピタゴラス音律が支配していた中世において、8度と5度、4度の3つだけが協和音程とみなされ、ほかの音程は経過的に使用されるだけであった。特に、ピタゴラス音律の3度は、81/64という高次の比率となり、不協和音程として扱われていた。このようにピタゴラス音律においては、音程に関してかなりの制約があったといえよう。数比的な秩序が、響きに対する感覚の自由さを妨げていたとも考えられる。ところが、ピタゴラス音律が支配的であったこの時代でも、この音律の制約を受けず、より感覚的な音程を保持していた地域があった。
イギリス・アイルランド地方では、フランスやドイツなどの大陸とは異なった傾向の音楽が展開していた。その大きな違いを生みだしたのが、3度(あるいはその転回音程の6度)に対するイギリス・アイルランド地方の人たちの好みなのである。彼らの好んだ3度は、ピタゴラス音律による不協和なものではなく、純正に協和する状態(すなわち5/4の比率)のものであったという。なぜ、このような純正3度に対する感覚をイギリス・アイルランド地方の人たちがもっていたかについては定かではないが、おそらく、この地方に移り住んだといわれるケルト人と関係があるように思われる。
………………………………(引用おわり)
ケルト人、カエサルの『ガリア戦記』に登場するガリア人(厳密にはケルト人とイコールでないといわれますが)は、はじめはヨーロッパのほぼ全域に分布していたけれど、ローマ帝国によって追いやられ、イギリスのアイルランドなどに極限されたとするのがこれまでの定説だったようですが、最近では、イギリスのケルト文明と大陸のケルト文明の相関に疑問が呈されることにもなっている……その点はちょっと気になりますが、この藤枝さんの本では、「3度の担い手」として、「ケルト」があったんじゃないかという仮説に立っています。もう少し引用を続けてみましょう(pp..86-87)。
(引用はじめ)………………………………
イギリス・アイルランド地方の民衆のなかで培われた純正3度は、「イギリス風ディスカント」という独特の歌唱法を生みだした。この歌唱法では、もとの旋律に対して、あらたな旋律が3度や6度の平行音程によってなぞるのである。すると、ピタゴラス音律では得られない豊かで甘美な響きが生み出される。(中略)14世紀から15世紀にかけて、この3度によるイギリス独自のスタイルは、イギリスを代表する作曲家のジョン・ダンスタブルによって、大陸へ伝えられたといわれている。そして、フランスにおいて「フォーブルドン」という技法を生み、純正3度の響きが大陸の音楽のなかにしだいに浸透していった。それにともなって、ピタゴラス音律によるそれまでのポリフォニーの響きが一変させられたのである。
純正3度の登場。それは、純正5度に基づくピタゴラス音律の支配を終わらせ、純正調の新しい時代の到来を告げるものであった。このような音律の変化は、また、中世からルネッサンスへの大きな時代の移行も意味していた。
では、なぜ、純正3度が大陸でこのように広まったのだろうか。それは多くの人々が、純正3度が生みだす甘美でとろけるような響きに魅了されたからである。ピタゴラス音律の厳粛で禁欲的な響きは、たしかに神の存在を暗示しながら、宗教的な活力を与えていた。しかしながら、響きに快楽性を求めた耳の欲求が、純正3度の音律を受け入れていったようにみえる。
15世紀になり、ポリフォニーのスタイルはさらに複雑になっていくが、それとともに、純正3度の響きは、そのポリフォニーに協和する縦の関係を生みだしたといえる。つまり、ピタゴラス音律のポリフォニーでは、絡み合った声部が分離して聴こえるが、純正3度が入り込んでくると、それぞれの声部が音響的に溶け合ってくる。その結果、ポリフォニーのスタイルが和音の響きとして、つまり、同時に響き合うホモフォニー的な傾向となっていった。イギリス・アイルランド地方からやってきた純正3度は、このように大陸の人々の耳に豊かで甘美な響きを与えながら、音楽スタイルの変化を引き起こすひとつの要因となった。
………………………………(引用おわり)
藤枝さんの本のこの部分をずっと読んでいると、まさにベートヴェンの第九の解説じゃないか……これは……という錯覚に囚われてしまいます。まあ、逆にいえば、このベートヴェンの第九交響曲というのは、作曲時点は19世紀初頭だけれど、実は、はるか古代から中世にわたる教会でのピタゴラス音律による単旋律聖歌、それが12世紀に入って5度のポリフォニーを生み、さらにルネサンスを迎えて3度音程による現代につながる西洋音楽の誕生(長3度の長調と、短3度の短調)……そのすべてを、70分前後の4つの楽章の中にとじこめた、いわば西洋音楽の古代から現代に至るタイムライン、時間圧縮タイムカプセルみたいな音楽だった……そんなふうにもいえるのではないか……
したがって、ここで考えなくてはならないのは、5度に象徴される「しばる力」(交感神経的)と3度に象徴される「ゆるめる力」(副交感神経的)の関係じゃないかな……と思います。この第九は、さらっとみると「3度の勝利」で、空虚5度にはじまる不安感、どうしようもなく頼りなく、けれどぎりぎりと縛られていくような不快感……そんなものが、最終的には「ヒューマニズム3度」で解決されて、人類はみな兄弟になる……戦争も仲たがいも争いも支配も服従もない、自由で幸福なエリジウムに入る……そんなふうにも読めるのだけれど、本当にそうなんだろうか……
ベルリンの壁崩壊直後のバーンスタインの演奏……そこにはたしかに、「自由に対する希求」が強く現われている。しかし、第二次大戦の終了まもないフルトヴェングラー盤は、聴いていてなぜか不安になる。バーンスタイン盤は、もうこれ以上ないくらいの肯定的感情が溢れかえっているものの、では、その後の世界の経過はどうだったか……そういうことを考えると、この曲の持っている性格は、もしかしたら意外に複雑なものなのかもしれない……そんな思いもしてきます。
たとえば、この曲では、第一楽章と第二楽章は、空虚5度が支配するメロディーの断片が飛び交う、まさに戦場のような雰囲気ですが、第三楽章に入ると突然、すべてが一変して、3度が支配する甘美なメロディーの洪水にみまわれます。なるほど、これがエリジウムの世界……私は、以前に見たイギリスの画家、ジョン・マーチンの天上世界の絵をどうしても思い浮かべてしまうのですが……しかし、作者のベートーヴェン自身は、この「3度の洪水」を無条件には肯定していない。
藤枝さんの本では「純正3度が生みだす甘美でとろけるような響き」とありますが、まさにこの第三楽章がそのもの(調律は純正調ではないけれど)……しかし、この響きは、第四楽章の冒頭で否定されます。第一楽章、第二楽章のメロディー断片を「これではない」、「これも違う」と否定したあと、流れてくる第三楽章の断片に対して「うーむ……いいんだけど、どっか違う。もっといいのはないんかい?」とくる。要するに、ベートーヴェンとしては、空虚5度が支配する厳格でオソロシイ世界はむろん否定するんだけれど、その対立項として現われる3度の甘美な世界も、そのままでは肯定する気になれんなあ……とそんな感じです。
私は、ここに、ベートーヴェン自身の人類の歴史(というかヨーロッパ文明の歴史)に対する一つの見方をみるような気がする。ベートーヴェンも、詩を書いたシラーも実はフリーメーソンだったとかいう話もありますが、そういうややこしいことを考えなくても……まあ、考えてもいいんですが、やっぱりもっと大きく、この時代に現われてきた、一種の自己批判的精神(文明の自己批判)ではなかったか……これは……19世紀という時代が、うちにそういうものを孕んでいて、それはいまだに解決されていない……そんなふうにも思います。
その一つの引っかかりとして、第四楽章に登場する「Cherub」(ケルブ、ドイツ語読みではケルプ)というヘンな?存在のことを考えてみたいと思います。これはむろん、シラーの原詩にも出てくるようですが、かなり位の高い(第2位)の天使だそうで、その天使が、神の前に立つ!(und der Cherub steht vor Gott.)ここです。この箇所は、合唱のなかでたしか3回くりかえされて、そのたびに感情が高まっていきます。
で、この歌詞の前にあるのが、Wollust ward dem Wurm gegeben. 快楽は虫ケラに与えられん、という一句。やや、これはなんだ……ということですが……私はここで、どうしてもあの第三楽章の「3度の甘美の洪水」を思い出してしまう。Cherub(天使ケルビム)と Wurm(虫)は対になってるように思えます。天使ケルビム(ケルビムは複数形で、単数はケルブ)は、「智天使」ともいわれ、「智」をつかさどる。その天使が神の前に立ちふさがって神を守る。虫けらども、ここはお前たちのくるところではない!と……
なるほど、感情の喜びに流されて知性も理性も失ったものは、本当の神の前にブロックされるということなんだろうか……そういえば、ここで思い出すのは、第四楽章の開始を告げる、あの「恐怖のファンファーレ」。第三楽章の甘美に酔いしれていた聴衆は、ここでドカーン!とその存在自体を葬りさられる……そんなふうに感じるほどアレは強烈で、私のようなバッハ以前の古楽が好きなものは、「あ、やっぱりベートーヴェン、ダメ」と、ここでスイッチを切りたくなる、そういう過激な……
譜面をみると、あの不協和音の構造がわかってきます。なんと、Dマイナー(D+F+A)とB♭メジャー(B♭+D+F)を同時に鳴らしている。鳴る音は、D、F、A、B♭の四つなんですが、AとB♭が半音でケンカしてあの不協和。しかも大音量で。Dマイナーは第一楽章、第二楽章の主調だからわかるにしても、B♭メジャーは? ということで譜面を見ると、これはなんと、第三楽章の調だった。つまり、この第四楽章の冒頭では、第一楽章、第二楽章、第三楽章の主和音を同時に鳴らすことによって、これまでの全部の音楽の総決算だぜ!ということを聴くものに告げ知らせる……

と同時に、これは、甘美きわまる第三楽章、B♭メジャーの徹底的な否定にもなっている。DマイナーをB♭メジャーに思いっきりかぶせることによって甘美な第三楽章全体を惨殺する……そんなイメージです。で、これが、第四楽章の後の方で、智天使ケルビムと虫けらの対比になって出てくる。ということはつまり、ケルビムは、もしかしたら Dマイナー、あるいは空虚5度そのものなのかもしれない。
ケルビムって、現代のふにゃふにゃアートではぽっちゃりしたかわいい天使の姿に描かれることも多いそうですが、旧約聖書に出てくるその姿は、まさに怪物そのもの。この天使は、創世記とエゼキエル書に出てきますが、エゼキエル書における詳細な描写は次のとおりです(以下引用。10章9-14節)
『わたしが見ていると、見よ、ケルビムのかたわらに四つの輪があり、一つの輪はひとりのケルブのかたわらに、他の輪は他のケルブのかたわらにあった。輪のさまは、光る貴かんらん石のようであった。そのさまは四つとも同じ形で、あたかも輪の中に輪があるようであった。その行く時は四方のどこへでも行く。その行く時は回らない。ただ先頭の輪の向くところに従い、その行く時は回ることをしない。その輪縁、その輻(や)、および輪には、まわりに目が満ちていた。-その輪は四つともこれを持っていた。その輪はわたしの聞いている所で、「回る輪」と呼ばれた。そのおのおのには四つの顔があった。第一の顔はケルブの顔、第二の顔は人の顔、第三はししの顔、第四はわしの顔であった。』(引用おわり)

これはまるで怪物……具体的な姿をイメージとして思い浮かべることは困難ですが、絵画作品として描かれたその姿は、たとえば上の絵に出てくるみたいな異様なもので、えっ、これが天使なの?という言葉が思わずでてきそうな……同じような「怪物」の出現は、エゼキエル書の冒頭(第一章)にもあり、そこでは、この「生き物」は「人の顔、ししの顔、わしの顔、牛の顔」を持つとされています。
しかし……この箇所をまともに読んでみると、もうこれはとても「天使」(現代の)のイメージではないし、「生き物」というにもほど遠い。なんか、機械装置、あるいは車か飛行機みたいな……ジョージ・ハント・ウィリアムソンみたいに、これこそ円盤、宇宙船にちがいないという人もいるんですが……
正直、どうなんでしょうか。ただ、この存在が徹底して「4」に関係することだけはたしかなようです。それと、「人の顔、獅子の顔、牛の顔、ワシの顔」がおそらくは、「水瓶座、獅子座、牡牛座、サソリ座」に関連することも。なぜなら、サソリ座は、古くは鷲座とされることもあったらしいので……
まあ、このあたりは、もしかしたら本質から遠い?のかもしれませんが、おそらくケルビムという存在は、神の前に立ち塞がり、神へのアプローチを妨害する門番みたいな役割であったことはまちがいないと思います。そして、それで思い出すのがやっぱりデミウルゴスとグノーシス……これについては前に書きました。リンク
そして、もう一つ気に留めなければならないことが……それは、智天使ケルビムが登場する前の、この箇所(かなりの超意訳をつけます)。
Wem der große Wurf gelungen,(大きな幸いを得た者よ)
Eines Freundes Freund zu sein,(真の友を得た者よ)
Wer ein holdes Weib errungen,(やさしき伴侶を得た者よ)
Mische seinen Jubel ein!(いざ、この喜びを共にせん)
Ja, wer auch nur eine Seele(そうだ、ただ一つの魂でも)
Sein nennt auf dem Erdenrund!(この地に、共にある!といえる者があるならば……)
Und wer’s nie gekonnt, der stehle(そしてもし、そういう魂を得られなかった者は)
Weinend sich aus diesem Bund!(忍び泣き、この輪から去るがよい)
これはけっこう厳しい……つまり、心が空虚5度に満たされて、この世界に満ちるこわばった掟(Mode)をふりかざし、真実の心の友も得られず、パートナーからも嫌われて、真の世界で孤立した者は、立ち去れ!……この地上に、お前のようなやつのおる場所はないのだ!と。しかも、「stehle」(英語のsteal)なので、大騒ぎせずにそっと消えてしまえ! ということで、空虚5度の心の持ち主に対しては容赦ない。
そして……3度の甘美に酔いしれる「虫けら」のようなヤツも、当然この輪には入れない……ということで、ここではじめて、この「第九」の大きな枠構造が浮かびあがってくるような気がします。つまりこの1時間超の大作は、全体として、空虚5度のガチガチの分断する心も、3度の甘美に酔いしれてふにゃふにゃになった心も、両方ともアカンと言っている。
さて……われわれ人類は、これからどこへ行くのだろうか……ベートーヴェンの時代には、すでにストレートな?神への信仰は失われはじめていたのでしょう。この第九では、vor Gott、神の前に、という言葉が何回も出てくるけれど、その場所に立っているのはあのおそろしいケルビム……すべての人が兄弟となる……しかし、それはなんによって?
ベルリンの壁が崩壊したときには、おそらく多くの人がそういう思い(万人皆兄弟)に満たされたのではないでしょうか。しかし……「すべての人が兄弟となる」世界は訪れなかった。いや、今の状況は、もしかしたらさらに深刻なのかもしれません。世界中で多発するテロや戦争……あいかわらずCO2を垂れ流し、資源を食いつくす人類……そして、あの身の毛もよだつゲンパツの大増殖……まるで、あの「恐怖のファンファーレ」そのもののような……
ベートーヴェンって、ホントに一筋縄ではいかないやっちゃなあ……そう、思います。第九の中にあるさまざまな「仕掛け」は、もしかしたらまだあんまり読み解かれていないのかもしれません。
たとえば……演奏者の間で、常に問題になる第四楽章の「vor Gott」がくりかえされる部分(上に述べた部分)。この箇所は、オーケストラも合唱もff(フォルティシモ)指定で目一杯、大音響でがなりたてる(失礼)のに、ティンパニだけはその部分にff > p つまり、フォルティッシモからピアノにディミュヌエンドしないさいという指示があって、これがために、みんなが大音響で「vor Gott!」と連呼しているなか、ひとりティンパニだけは少しずつ音を弱めながらさびしく消えていかねばならない……
実は、この指示は、かなり最近まで定番楽譜として用いられてきたブライトコップフ版にあったそうですが、最近出されたベーレンライーター版では、ティンパニも一緒にffしましょうという指示になってる。で、これで喜んだのがティンパニ奏者の方々で、なんでオレだけ……という鬱屈した思いを吹き飛ばすようにティンパニの強打……指揮者の中にも、なんでティンパニを p にせにゃならんの?という理由がわからなくて、ブライトコップフ版の指示を無視してティンパニも ff でやってこられた方も多かったとか。
しかし、この部分の前の歌詞の意味を考えてみると、上のように、神の前に立つケルビムに拒まれて立ち去らねばならないものがいるわけです。これは、私の解釈では、Mode(世の掟)にガチガチになった空虚5度の石頭連と、逆に3度の甘美に酔いしれてふにゃふにゃになった虫けらども……となるわけですが、もしかしたらティンパニに与えられた ff > p の指示は、こういう連中がさびしく去っていく姿を、音楽表現の上でやらせている……そういう解釈も成り立つのでは?
この箇所は、昔から演奏者の間では大問題だったらしくて、音量バランス上の問題とかいろいろ言われてますが、歌詞の内容に関連した表現ではないかという解釈は、私はみたことがない。でも、フツーに単純に考えれば、そうなるんではないだろうか……そもそも、ベートーヴェンの楽譜の校訂作業というのは困難を極めているそうで(自筆譜や献呈譜やいろんな出版譜があるので)、文献上からこうだ!という決定はできないそうなんですが……しかし、もしこの箇所で、ベートーヴェンがなにも考えてなかったら、当然ティンパニの ff > p という不自然な指示が生まれるはずはない……ということは、この ff > p にはやっぱりなにかの表現意図がある……そう考えるのが自然ではないかと思うのですが。
まあ、音楽の専門でない私の思いつきなので、なんともいえないのですが……音楽は、聴けば直接になにかが伝わってくる。それはたしかです。しかし……演奏する人も、聴く人も、もしかしたらそこに鳴っているその音楽の中に、なにかかなりのものを聴き逃しているのかもしれない。聴く方はともかく、そういう、よくわからない状態で演奏ってできるの?ということなんですが……でも、今も、たくさんの指揮者、演奏家、声楽家が、世界中で「第九」をやってます。で、さらにさらに多くの人が聴いている……
演奏技法の問題だけではなく、この曲には、とくに第四楽章のケルビムが出てくるところで、私には、先に書いたように、デミウルゴス、グノーシスの問題がかなり本質的にからんでいるように思えてなりません。これは、西洋世界にとっては、やっぱり古代から今に続いて、まったく解決されていない大きな問題のように思いますが……すくなくとも、この「第九」は、従来言われている「人類愛」とか「ヒューマニズムの勝利」みたいな歯の浮くようなウソくさい言葉では歯が立たない、ややこしい巨大な問題を抱えこんでいるように思えます。
この第九の「ナゾ」、いったい解明される日がくるんだろうか……またいつの日か、続きを書ければ……